�@
�@![]()
������͏����̐������̂���
�u����ۂޕ����猾�킹�܂��Ǝ��͕S��̒��A�ۂ܂ʕ����猾�킹�܂��Ǝ��͖������J���i�ĂȂ��Ƃ�\���܂��āE�E�E�v������j�t�c���t�����w���x�̂܂���ł��B����ɂ͂ǂ������A�������悭�o�ꂵ�܂��B����̃X�g�[���[�́A�̂̏����̐������̂��̂ł��B���ꂾ���A���{�l�̐����ɂ����͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł������Ƃ������Ƃł��傤���B
�����w���x�ł͂�����ۂނ��߂ɂ݂�Ȃ����낢��Ȓm�b���o�������āA���ꂼ�ꂪ���̍���������܂��B�܂��A�w�n�R�Ԍ��x�ł͂����̑���ɂ����������Ɍ����ĂĉԌ��ɏo������n���ł��B
�w�q�ق߁x�͂������������Ă��炤���߂Ɉꐶ�����ɐl�̎q����J�߂�����܂��B�w���̂����x�͂�����ۂ߂Ȃ��j�����̂�����H�ׂĎ���ۂƎ������悤�Ƃ��锶�B�w�֎��֏��x�͋֎�߂̂����ꂽ�鉺�̊֏����������m�b���i���ĂȂ�Ƃ��˔j���悤�Ƃ��܂����A�w��Ԑ����x�ł͎�����@�x�̔ԏ����Ő�����ƋU���Ď���ۂ����Ƃ��܂����A��l�Ɍ��j���Ă��܂��܂��B
�w��x�̑O���͈������ƍ�������������Ƃ������ł����A���̕����������w�������x�Ƒ肵�ĉ������邱�Ƃ�����܂��B�w�ߊ�̎ϔ��艮�x�ł́A�|�����ȍ�Ŏ���ۂ�ł���p�����āA�������^�_�œ��������ɓ���悤�Ƃ����j�����s���锶�ł��B
�����̔������ł��A����̓o��l����������ۂނ��߂ɗ܂��܂����w�͂����Ă���̂��킩��Ǝv���܂��B
�������闎��Ƃ́E�E�E
�����闎��Ƃ��A�����ł͂��Ȃ��J�����Ă���悤�ł��B�����Ƃ����A��͂荡�͖S���U��ڏΕ������ߎt���ł��傤�B�����Ƃ���ɂ��ƁA���ߎt���͂W�ŋ������̒g�����������������ŁA����ȗ��A�����������A�����ɂ܂�闎����D��ł���Ă����܂����B�ۂ݂��Ղ�͂Ƃɂ��������������悤�ł��B����邩�Ȃ������Ă����t���͋C�ɓ���Ȃ����Ƃ�����A����q������{�R�{�R�ɉ���܂����B�����A�t���͂��̒�q�{�l�Ɂu�Ȃm��ǁA���N������肪���̂������ɂ��˂�v�ƕs�v�c�����Ɍ����������ł��B
���̏��߂̖��Ղ��P�����邱�ƂɂȂ����Ε������t�����i���F���t����͂��̋L���̔��s�̌��Ɏ����A�v��ɂV��ڏ��߂̖��Ղ�Ǒ�����܂����j������Șb������܂��B���͏��t����A����ƂɂȂ�O�́A�^�L���r�[���H��ɋ߂Ă����̂ł����A�ł����Ă̏��i�����t���t���Ɠ��ݓۂ݂��Ă��܂��A���ꂪ��ĂR�����őގЂ����Ƃ����{�����E�\���킩��Ȃ��G�s�\�[�h�ł����B
���������ߎt���̂���q����̏Ε������}����́A�����D�P�������A�j�̏��}�������肪�Ђǂ������̂ł����A�����̍s��A�ł́u�����A����������B���J���t���[�W����v�ĂȂ��Ƃ������Ă��������ł��B
�܂����̐l���̐l�ł����A���̗щƏ����������Ȃ̈����ł͗L���ł����B���ނ̑��o�D���̏�������́A�����A�t�R�Ƃ����͎m�ƍ��ӂɂ��Ă���A�悭��l�œۂݖ������������ł����A�����������̂͊֎�̕��ŁA���ɏ������ڂ��o�܂��ƁA�������E���U�炩����������������Ƃ�����ł����������ł��B
������҂ɂȂ�ʂ悤��
�Ε������V���t���Ȃǂ́A�����ς���č����ɏオ��A���̓r���Ŗ����Ă��܂��Ƃ����A�M�����Ȃ��h�W��ł��܂��B
�j�t�c���t�������Ȃ�̎����ł������A�ݒ�ᇂ������Ă���́A�������Â����Ɏ���o���悤�ɂȂ�A����q������t���̏��ւ͂����ς�Â����������čs���悤�ɂȂ�܂����B�������Ŏ���̐l�́u���x�͓��A�a���S�z��ȁv�Ƙb���Ă��邻���ł��B
�����ς炢�����ɂ��܂������闎��Ƃ��A�������ŗ���̓o��l���ɕ����Ȃ����炢���̏�̃h�W��ł���悤�ł��B���Ƃ́A��͂肻���������s���|�̔�₵�ɂ��Ă���̂ł��傤�B�Ƃ͌������̂́A����ł̎��̎��s�͏��čς܂����Ƃ��ł��܂����A�������ɂ�������̎��s�́A�l����������ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��̂ŁA�ۂ݂����ɂ͂��ꂮ����䒍�ӂ��B�@�y�Â��z
�y�P�X�X�U�N�X���@������u�V�C�[���v��T�O���i�����������̊y���ݕ� �S�W�j�Ɍf�ځ@�z
![]() �@
�@
�������Ȃ�ł̖͂���
�����Ƃ������̂͐l�Ƃ��t�����������邤���ŁA�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂Ƃ����悤�ɐ̂��猾���Ă��܂��B���ɓ��{���́A����Ƃ���������ۂ݂܂��̂ŁA�R�~���j�P�[�V�����ɂ͂����Ă����ł͂Ȃ��ł��傤���B�t�����킷���Ƃɂ��A�����m�炸�̐l���m���A���ɂ��ċ��m�̗F�̂悤�ɒ��ǂ��Ȃ��̂����̌��p�ł��B
�w�x�ł́u�������v�Ƃ����������o�ꂵ�܂��B���̒��ł͋M�d�ō����Ȃ����Ƃ����悤�ɂȂ��Ă��܂����A���ۂɓۂ�ł݂�ƁA�����Ƃ�����薡���Ƃ��������ŏ����ۂ݂Â炢���̂ł����B�w����ƂĂ���x�͒m�������Ԃ�̒j�̕@�����������߂ɁA�����������薼�Y�ƋU���Ă��̒j�ɐH�ׂ����锶�ł����A���̒��Ɂu���s�������̔��e�v�Ƃ����������o�ꂵ�܂��B�u���炬���v�Ƃ��������͑S���ɂ������i
����ۂ݂��\�l�\�F
����̒��ɂ́A����ۂ݂����Đl�ɗ���Ŗ��f�������锶�������܂��B�w�Z�g���āx�ł͉��Ă��������������ɗ��܂�ĉ������܂����A�w�������ǂ�x�ł͒ʂ肪����̐����ς炢���A�w�e�q���x�ł͐����ς炢�̑��q���A���ꂼ�ꂤ�ǂɗ���ō��点�܂��B�w�S�l�V��x�ł͈ɐ��w��̓r���Ɏ��������ł��ɂȂ��Ă��܂��܂��B
����ۂ݂����Ė{�l�����s���锶������܂��B�w���܂̖��x�ł͎���ۂ݂������K�}�̖����肪�����ł������̌����~�܂�Ȃ��Ȃ��ĉE���������܂����A�w�s�����x�ł͎s�������������ĉ̗p�S�̖���ɏo�Ď��s���܂��B�w�M�ٌc�x�ł͏��[�ɉB��ďM�V�т����Ă����j���͂߂��͂����߂��ď��[�Ɍ�����v�w���܂ɂȂ��Ă��܂��܂��B
������ۂݏo���Ǝ~�܂�Ȃ��Ȃ�l�����\����܂��āA�w��l��x���w�L�̍Г�x�ł͂�����Ƃ��߂ɂ��Ă��܂��A����𑼐l��L�̐ӔC�ɂ��Ă��܂��܂��B�w�炭���x�ł͋C�̎ア������������ۂ�ŕ^�ς��A���ʂ̌F�ܘY�Ɨ��ꂪ�t�]���Ă��܂��܂��B�w�������x�ł́A�܍��̎���ۂ߂邩�q�������j���A�{���ɓۂ߂邩�ǂ����A���̌܍���ۂޒ��O�ɁA�����ɕʂɌ܍��̎������݊����Ă��܂��Ƃ��������̔��ł��B
�܂��A�ق̂ڂ̂Ƃ�����ۂ݂̔�������܂��B�w�ւ�ځx�ł́A�����������j���ЂƂ茾�ŏ��[�Ɏ����̓����̂킪�܂܂�l�сA���ӂ��Ă���p�����[�Ɍ����Ă��܂��ďƂ��Ƃ����{���ɏ�̂��锶�ɂȂ��Ă��܂��B�w�h�ւ��x�̒��ɂ͂����͑S���o�Ă��܂��A�����z���Ɏ����̕��e��A��Ă���̂�Y�ꂽ�j���A�אl�Ɂu�킪�e��Y���l�����܂������ȁv�ƌ����A�u�e�Ȃ�ĉ��ł����܂ւ�B���ȂA����ۂ���Y��Ă��܂��܂��v�Ƃ����̂����̃T�Q�ɂȂ��Ă��܂��B
���̂悤�ɁA����̒��ɂ͂������d�v�ȏ�����Ƃ��Ċ��Ă��܂��B����ɂ����Ď���ۂގd���A�����Ď���ۂ�Ő��������Ă����l�͂��Ȃ�̉��Z�͂��v������܂��B������ǂ̂悤�ɂ��܂������邩�ɗ���Ə����͋�J����Ă���悤�ł��B
�����͓ۂ�ł��ۂ܂��ȁI�H
����ɂ����鐔�X�̎��̎��s�k�Ƃ����̂́A�������ɑ���ۂ݂����ւ̌x���ł���悤�ȋC�����܂��B�K�ʂ̂������y�����ۂނ̂���Ԃł��B��������A�u���͕S��̒��v�ɊԈႢ����܂���B
�Ȃɂ͂Ƃ�����A�����낢����Ɏ|����������A�l���́u�܍������v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���A���̂��Ƃ�āH�@�u�܍������v�Ɉꏡ���͋l�܂�܂���B�ł�����A�u�܍������v�Ƃ́u�܂��ꐶ�v�Ƃ������Ƃł��B
����ł͊F������u�܍��i�܂��܂��ɐ��j�v�����F��\���グ�܂��B����ł́A���オ��낵���悤�ŁE�E�E�B
�y�P�X�X�U�N�P�O���@������u�V�C�[���v��T�P���i�����������̊y���ݕ�
�S�X�j�Ɍf�ځ@�z
�@
���̉�グ�ނ̊����ɂ��āA���̏�u����y���v�����ނ��A�Q�O�O�O�N�T�����Ɍf�ڂ���܂����B���̓��e�ɂ��ẮA�u����y���v�̂g�o�ɃA�b�v����Ă��܂��B
�@�u����y���v�g�o�u���̉�グ�ށv��ދL��
�O�g�t�v����Ȃ�����ǁA�킪�w���̉�グ�ށx�͉������Ă������邨�q����̉�����Ő������Ă��܂����B�������̃}�N���Ŏ��X�����܂����A�ŏ��͖{���ɂQ�`�R�l�̂��q����̑O�ʼn����Ă����O���[���v���U�������P���ق́w�w�O��ȁx������ɂ��q����̐��������A���ł͏�ɕS���\�l�̕��ɂ����ꂢ�������A�傫�ȂS�K�̑��ړI�z�[���������ɂȂ邭�炢�����ɂȂ�܂����B���̂����A�O���[���v���U�̂��ׂ̍��Ύs�������s���𗬃Z���^�[�ł�����i�w�w�O��ȁx�͋������j�Ɂw���Ύs����ȁx���J�Â����Ă��������Ă���܂��i���P�j�B����A�吨�̂��q����̑O�ŗ��ꂪ�o���邱�Ƃ͖{���ɍK���Ȃ��Ƃł��B
�������w���̉�グ�ށx�̃����o�[�́A����������������y���ނƓ����ɁA���̂��q����Ɋy����ł����������ƁA�y����ł������������q����A����ɂȂ��Ă����������ƂɈ�l��l�����S���ĎQ��܂����B���̌��ʂ����̐����Ԃ�Ɍ��т��Ă���̂��ƐM���Ă��܂��B�f�l�̗���T�[�N���Ƃ����ǂ��A�ЂƂ�悪��Ȏ��Ȗ��������ł́A���ꂾ����𑱂��Ă��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ł��傤�B���̓_�A�e�l�ɂ��Y�݂��J������ɈႢ����܂���B�����������������Ԃ�ƔY�݂܂����B��̑����Ɋւ�邱�Ƃ����x������܂����B
�����S�N�ɃX�^�[�g�����w�w�O��ȁx�ł����A�����V�N�Ɏ�Î҂�����Җ�����������܂��H���鎖�����N����A�����Ɏ������̂ŕm���̏d�����Ƃ����A�N�V�f���g�ɂ݂܂��A���̉�A�V���w�w�O��ȁx�Ƃ��Ĉꂩ��ăX�^�[�g�Ƃ������ƂɂȂ�܂������A���낪�����ē�����Ȃ��̂ŁA���R�A���q����̐��͌���܂����B���]�̍�ŁA�����ӂ̉ƒ�Ƀr���z������邱�Ƃɂ��āA�Q�`�R��������Ő��S���̃r����z��܂������A�قƂ�nj��ʂ͂Ȃ��A���q����͌����B�w�w�O��ȁx�����O�̓����ƈÂ��C�����Ńr���z����R������������́w�w�O��ȁx�̓��A�J�ꂵ�Ă��Ȃ��Ȃ����q�����Ȃ��Ȃ��Ɨ�������ł���ƁA��l�̂��������̔z�����N�V���N�V���ɂȂ����`���V����Ɏ����ė��Ă���܂����B�ق�Ƃɂ��̎��́A�܂��o��قNJ����������ł��B����܂ł̋�J���A���ʂłȂ������Ƃ����������u�Ԃł�����܂����B
���̌�A���R�~��n���̃~�j�R�~���̉����āA���X�ɂ��q����̐����������Ă�����Ȃ�ł����A���̉A�ł́A��͂莄���x���Ă��ꂽ�X�^�b�t�̑��݂��傫�����̂�����܂��B���������ɂ�A�����o�[����l�܂���l�Ƒ����Ă��āA���ꂻ��̃����o�[���X�^�b�t�Ƃ��Ċ撣���Ă���Ă��܂��B�܂��A�e�l�������ɏo���邱�Ƃ��l���čs�����Ă��������Ă���̂ő�ϐS�������Ƃł�����܂��B����ɉ����āA�w�w�O��ȁx�̉�����Ă�������O���[���v���U�������P���ق̓��X�҉�y�э��Γs�s�J���i���j�̊F�l�A�w���Ύs����ȁx�����Â��Ă�������i���j
���낢��Ƌ�J�͂���܂����A��������̂��q����ɗ��Ă��������A�����āA���q����̏Ί�A�u�y���������v�Ƃ����ꐺ�A��܂��̂����t�A���ɂ͍�������i�H�j�Ȃ������Ɋ������A����܂ł̋�J��Ȃ�S�ĖY�ꂳ��Ă���܂��ˁB��͂�A�u���q�l�͐_�l�ł��I�v
���u���̉�グ�ނ̕����v�����Q�Ƃ��������B�@
�i���P�j�u�w�O��ȁv�̉��́A�����P�V�N�P�Q���S���������ΐ����S�ݓX�U�K���ړI�z�[���Ɉړ]���A
�@�@�@�@�u���Ύs����ȁv�̉��́A�����P�T�N�U���P�����琶�U�w�K�Z���^�[�Ɉڊǂ���܂����B
�i���Q�j���݁A�u�w�O��ȁv�͐������ΕS�ݓX�A�u���Ύs����ȁv�͍��Ύs�����U�w�K�Z���^�[�ɂ����b��
�@�@�@�@�Ȃ��Ă��܂��B�y���������ǂ́u����𑠂݂�`�����ށv�́A�����P�W�N�P���P�T���ɕق��܂����B
![]()
�|�\�Ɍ��炸�X�|�[�c��������W�������ɂ̓v���Ƃ������݂�����B�v���ƃA�}�̈Ⴂ�͉��Ȃ̂��B���ɗ���ɂ�����v���ƃA�}�͂����ɈႤ�̂ł��낤���B����Ă��邱�ƂɈႢ�͖����B���q����̑O�ō��z�c�ɍ����ė����������̂ł���B�ȒP�Ɍ����Ă��܂��A�v���͂��̌|�ɑ��Ă������Ƃ�B�������ꂾ���ł���B�������A���ꂪ����B�v���ƃA�}�̎��͂̍��͂����đR��ׂ��Ȃ̂ł��邪�A�����͂����Ȃ��B�A�}�Ƃ�����l���v���̎��͂𗽉킷�邱�Ƃ��ԁX����B������A�������Ƃ�ɒl����|���o���邩�ǂ����Ƃ������Ƃ��v���ƃA�}�̈Ⴂ�ł͂Ȃ��B
�A�}�`���A�ƌĂ��l�́A�ʏ�͌|�ȊO�Ɏ����̎d�����������Ă���B�d���������Ȃ���ł��|�Ŏ�����Ƃ����̂́A���h�ȃv���ł���B�A�}�͌|�ȑO�ɂ܂������̎d���̎����l����B�܂�A�d�������Ă̎�̐��E�Ȃ̂ł���B���R�A��̂��߂Ɏd�����]���ɂ��邱�Ƃ͋�����Ȃ����A�Љ�ɂ����Ă����ꂾ���̐ӔC����������Ă���B���̓_�A���̓I�ɂ����_�I�ɂ����Ȃ萧��������B��Ƃ́A�����������X�g���X���������邱�Ƃ̂ł��鑶�݂ł��肽���B�������A�]�ɂ̑S�Ă���ɂ��ĂĂ��܂��Ƃ����̂͂��ꎩ�̂��X�g���X�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȋC������B
�@
�v�����A�}�����q������y���܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A�v���͂ǂ̂悤�Ȍ|�ł���A�ł���A���q������y���܂���Ƃ����`�����B�A�}�͂܂��������y���ތ��������B����͑傫�ȈႢ�ł���B�ł��A��邱�Ƃ͓����Ȃ̂ł���B�v���͓��R�Ȃ���|����X���r���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�A�}���l�O�ʼn�����ȏ�A�|���͓̂�����O�ł���B���ƌ����āA�A�}�Ƀv���̏C�s��d����������v����͔̂n���������Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@
����Ɋւ��āA�A�}�̍����Ɋ����Ƃ������t�͕K�v�Ȃ��Ǝv���B����͊Â����ƌ�������̂Ƃ��肾���A�t�Ɍ����A���ꂪ�f�l����̗ǂ��ł��邵�A�܂��A�����N���邩�킩��Ȃ��Ƃ����y���݂�����B���̊Â��̓v���ɂ͋������͂����Ȃ��B�f�l��Ȃɗ��邨�q����́A�����܂ł��f�l�͑f�l�Ƃ��Ă̍������y����ł�����B����������A�f�l��Ȃ̂��q����́A����������Ɋӏ܂���Ƃ�������ł͂Ȃ��A���҂ƂƂ��ɗ�����y���݁A�f�l�̔��Ƃ������ďグ��Ƃ������C�����������悤�ȋC������B����Ƃ����|���ɂ߂����Ƃ������́A�����炭���X�������ꗿ���Ăł��v���̊�Ȃɍs�����ł��낤�B
�@
�u�A�}�̓v���ɂ��炸�v�Ɛ����Ɍ����Ă݂��Ƃ���ŁA�u�|�Ɍg������́A�v�����A�}���ς��Ƃ���͂Ȃ��B�]���āA�A�}���v�����݂̎��͂�g�ɂ���ׂ��A����A�|�̓��ɂ������܂˂Ȃ�Ȃ��v�ƌ�����A���R�̂��Ƃł���B����A���ɓ��R�̂悤�ɕ�������B�m���ɂ��̃Z���t�́A���ˉ���́w���̌��x�̈��ĂƓ����ł���B���̌��t�𗁂т�����ƕ�����������A����ɕԂ����t���Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B�����ŋc�_�͏I����Ă��܂��B�Ƃ������A����ɔ��_���邱�Ƃ͋�����Ȃ��̂����m��Ȃ��B
�@�@
�A�}�Ńv�����݂̌|��Nj�����̂��A����͂���őf���炵�������Ǝv�����A���������l�ɂ͐���Ƃ�����߂����Ă������������B�������A�����̌|�ɂ����玩�M�������Ă����Ƃ��Ă��A���ՂɃv���̌|�̔ᔻ�͂��Ăق����͂Ȃ��B��������Ɍg���҂Ƃ��āA�A�}�Ƀv���̌|��ᔻ���鎑�i�͂Ȃ��Ǝv���B�v���̌|�������猩����Ă����Ƃ��Ă��A�v���̓v���B���F�A�A�}�̓A�}�Ȃ̂ł���B�P�Ƀv���̌|���y���ނ��q����Ƃ��Ă̗���Ȃ�D�����������邾�낤���A�ǂ�Ȃ��Ƃ��������ƍ\��Ȃ��B����ł��A�}�`���A�̗���ƂƂ��āA�����ăv���̌|��ᔻ���A�A�}�ɂ��v�����z����|�����߂�̂ł���A�|�j�肩���m��Ȃ����A����������̉��ɂ��܂��Ă���w�т̌���x���o������Ȃ��B
�@
�u�|�̓����ɂ߂悤�Ǝv���̂ł���A���Ȃ����v���ɂȂ�����I�v
![]()
���Ɨ���
���X�A���Ύs�ł͗����̂悤�Ȃ��̂͂��܂芈���ł͂Ȃ������悤���B���̋L���ł́A�N�ɂP�`�Q��̃v���̉���������炢�ł���B�ŋ߂́A���̕���⏬���Ȋ�Ȃ��悭�J�Â����悤�ɂȂ��Ă���B���������n��̗���̐U���ɂ��ẮA����w���̉�グ�ށx�����Ȃ��炸�v�����Ă���Ǝv���Ă���B�����̊�Ȃ̊J�ÂŁA���ד���Ґ��͂��������P���l�ɒB���鐨�����B
���ŗ��ꂪ�����łȂ����R�Ƃ��āA�܂����ɍ��Ύs�̈ʒu�I�Ȃ��̂��l������B���Ƌ��s�̂��傤�ǒ��ԂɈʒu���Ă���A�̂͐l�������Ȃ������̂ŁA�l���W�߂˂Ȃ�Ȃ����s���̂͂��܂萷��ɂȂ�Ȃ������悤�ł���B����͋ߔN�ɂ����Đl�����������Ă����l�ŁA�ʒu�I�ɒ��r���[�Ȋ��͔ۂ߂Ȃ��B
���ɏZ���̋C���ɋN�����Ă���Ƃ������Ƃł���B���Ύs�̎s�́i
��O�ɒn���o�g�̔��Ƃ����Ȃ����Ƃł���B����͓�Ԗڂ̗��R�Ƃ��֘A�Â��o���邩���m��Ȃ����A��͂�A���Ώo�g�̔��Ƃ�������A����Ȃ�ɒn���ł��������Ă������̂Ǝv����B�Ƃ������A���Ώo�g�̔��Ƃ������Ă��A�����͂قƂ�ǂ��d���ɕ֗��ȑ��s�����t���̉Ƃ̋ߕӂɈړ]���Ă��܂��Ƃ������Ƃō��Ƒa���ɂȂ��Ă��܂��Ă���B
�ȏ�̗��R����A���Ύs�ł͗���Ƃ��̌|�\�͂��܂荪�t���Ȃ������悤�ł���B���ɗ��R������̂����m��Ȃ����A���͂��̂悤�ɐ������Ă���B�ÓT����ɂ��قƂ�Ǎ��̒n���͓o�ꂵ�Ă��Ȃ��̂����̗��t���ɂȂ邩���m��Ȃ��B�����Ă�����Ƃ���A�u�h���w�v�Ɓu�v���炢�ł���B������A�u�h���w�v�ł́A�����̉\�b�Ƃ��āu���Δ˂̏����F��Y�v�Ƃ����l���ɂ܂��b�������̂ł���A���ۂɗ���̕��䂪���ł����ł͂Ȃ��B�u�v�Ɏ����ẮA�M���O�Ƃ��āu����v�Ƃ������t���u���s���v�Ɵ����Ĉꌾ�u�����̉ł͂�͋��ǂ��납���ւ��s���Ă܂ւ�v�Ƃ����Z���t�݂̂ŁA������A���҂���̏ꏊ�ɂ���đ��̒n���ɂ��낱��ς��̂ŁA���̒n�����o��Ƃ͌���Ȃ��̂ł���B���ꂾ���A����ƍ��͉������ԕ��������悤�ł���B
![]()
�j���̗�l�Ƃ����u��ˉ̌��v�A���`�Ƃ����u�̕���v����\�I���݂��B���l�Ƃ��Ắu��ˉ̌��v�̒j���̗�l�ɂ͏��X��a����������B�j�̗��ꂩ�猩�Ă���Ƃ������Ƃ����낤���A���Ȃ薳�������Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B������ƌ����Ĕے肷�����͂Ȃ��B�u�̕���v�ɂ͏��`�����X�Ƒ��݂��Ă���̂�����B�����܂ŁA���l�̎�n�D�̈�ł���B
����ł́A�u�̕���v�̏��`�͑S�ʓI�ɍm�肷��̂��ƌ�����A���������a�����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�������A������͎���̗v�����������Ƃ͌����A�����`���ɂ����グ��ꂽ�|�ł���A�m�肷�邾���̗��R������Ǝv���B�]�ˎ���̎ŋ��ɂ����ď���������ɏo���Ȃ��Ȃ����K�v��A�d���Ȃ��j�����������ĉ����Ă����̂ł��邪�A����́A�����Ƃ��Ă̕s���R������菜���A��������Nj����Ă��������ʂƂ��āA���݂̏��`�Ƃ��Ă̌|�������������̂ƌ����邾�낤�B�u�̕���v�̏��`���ŋ��̒��ŏ����炵������Ă����i�����ɂȂ肫��H�j�̂ɑ��āA�u��ˉ̌��v�̒j���͒j���������Ă��Ă��A�����܂ŏ����̖{���I�Ȗʂ͉B������Ă��Ȃ��B�����āA�����������o�����Ă���̂����m��Ȃ��̂����A�j�������A�j���̌��t���g���Ă��Ă��A��͂菗���Ȃ̂��B
����́u����v�ɂ��Ă�������B���Ƃɏ��������ɏ��Ȃ��Ƃ�����������L�̘_�@�����Ă͂܂��Ă���悤�Ɏv���B�u����v���u�̕���v�̉e����傫���Ă���A�]���āA�d�����u�̕���v�̉��Z���@��������Ă���ƌ����Ă��悢�B�u����v���u�̕���v�Ɠ��l�ɒj�̐��E�ł���A�u����v�ɓo�ꂷ�鏗����������̂ɁA���R�A�u�̕���v�̏��`�̎d���Ȃ����̂܂ܗ��p����Ă���B�Ƃ������Ƃ́A�u����v���u�̕���v�Ɠ��l�ɁA�j����������������|�����m������Ă��Ȃ��̂ł���B������A�������t�ɒj����������Ɖ��ƂȂ���a����������̂ł���A���q����̑z���͂Ɉˑ�����u����v�A���Ɂu�ÓT����v�̐��E�ł͓�����Ƃł���ƌ��킴��Ȃ��̂����m��Ȃ��B�����̉�����u�ÓT����v�͂ǂ����Ă��u��ˉ̌��v�I�ɂȂ��Ă��܂��B����ł��A�ŋ߂͊e����ł̏����̐i�o���߂��܂������̂�����A�����̗���Ƃ��u�n�엎��v�����낢��ƍH�v�����āA���̈�a���@���悤�Ɠw�͂���Ă���悤���B
�]�k�����A�����ꎞ���A��������ő����ɋA��Ă������Ƃ�����A�ߑO�T���S�O������A����̂Ƃ���w�ŏ�Ԃ��Ă��鍂�Z�����̏������Q�������B�����ł����邵�A�ޏ���͌��邩��ɑ��̏��q�����Ƃ͕��͋C������Ă����̂ł���B��l�̓{�[�C�b�V���Ȋ����Ŕ��̓V���[�g�J�b�g�A������l�͂���l���Ŕ��̖т͏������������ł������ăJ�b�`���ƌł߂Ă���B��l�Ƃ��w�������A���Ɏp���������̂��B�܂�Łu�d�J�K�[���I�H�v�ƈ�u�v�����B�����������d�Ԃ̓����ԗ��ɏ�荇�킹���B�ӂƁA�ޏ���̋��̃o�b�W������ƁA�u�s�l�r�v�Ə�����Ă���B�܂�A�u��ˉ��y�w�Z�v�̐��k�������̂��B�w�z�i���j�Ƃ����x�Ƃ������t�́A���������ޏ���̂��Ƃ��w���Č������t�Ȃ̂��Ȃ��Ǝv�킸�[�������B
![]()
������Ёu�O���R�[�|���[�V�����v�̏�u�`�l�i�A���j�v�̎�ނ��A�Q�O�O�S�N�V�����Ɍf�ڂ���܂����B
�@��u�`�l�i�A���j�v�Q�O�O�S�N�V�����f�ڂ̋L��
![]()
����ƃp�\�R���c�H�@���܂�֘A���Ȃ��悤�����A���̐��̒��͂���������ɂ������Ȃ��B����A�v���̗���Ƃ��z�[���y�[�W���J�݂���͓̂�����O�ɂȂ��Ă��邵�A��`�E�L��ɂ͌������Ȃ����f�B�A�ƂȂ��Ă���悤���B�A�}�`���A�ɂ�闎��̃z�[���y�[�W�����Ȃ��Ȃ��B
�܂��ƂɃC���^�[�l�b�g�̈З́i���́j�͂��������̂�����B���������f�l����̃T�[�N���ł��铖����z�[���y�[�W�̂������ŁA���{�S���݂̂Ȃ炸�A���E�I�ɂ������͈͂��L�����Ă���B����͑傰���ł����ł��Ȃ��B���ہA�h�C�c�ݏZ�̓��{�l���y�Ƃ̕��ƒm�荇���ɂȂ��āA�������ꂽ�ہA�����̉�̊�Ȃɂ��킴�킴���Ă������������A���{�̕������p��ŏЉ��T�C�g�̗��ꕔ��̉f��������̊�Ȃ̖͗l�����ꂽ�i���F���݂͔z�M�I���j�B�����ɂ����Ă��m�g�j���n�ߐV���Ђ�}�X�R�~�E�~�j�R�~�W�̎�ނ����z�[���y�[�W���_�@�ɂȂ��Ă���B���̑��A���{�����痎��Ɋւ��鎿��Ȃǂ���������悤�ɂȂ������A���݃����N���ɂ��S���̗��ꈤ�D�Ƃ̕��Ƃ̗ւ��L����A�o�O��Ȃ̈˗����قƂ�ǂ��C���^�[�l�b�g�o�R�œ����Ă���B�����āA����̌������o�[�̔����̓C���^�[�l�b�g�ŏW�܂����悤�Ȃ��̂ł���B
�����������Ƃ�����A��ʂ̗���t�@�����C���^�[�l�b�g�ŗ���W�̃T�C�g�����\���Ă����邱�Ƃ��悭���邵�A����̃t�@���Ȃ炸�Ƃ��ƒ�ŗ���Ɋւ���^��i�Ⴆ�A�u�������v�̖��O�̑S���j�Ȃǂ�����A�C�y�ɃC���^�[�l�b�g�Ō����ł���B�����Ŕz�M����T�C�g�Ȃǂ�����A�Ƃɋ��Ȃ���ɂ��ė��ꂪ�y���߂�悤�ɂ��Ȃ����B�܂��A�l�b�g��ɂ͗���̑��L�Ȃǂ���������A���̃l�^���d����鎞�ɂ͎������傭���傭���p�����Ă�����Ă����肷��B�C���^�[�l�b�g�ł͊�Ȃ◎��Ɋւ���������W����ɂ͎������Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A�ÓT�|�\�I�ȗ���ƌ����ǂ��A����𗘗p���Ȃ���͂Ȃ��B�n���ɗ������J�Â������邱�Ƃ͑厖�Ȃ��Ƃł��邵�A���R�~�̗͂��d�v�ł���B�������A�C���^�[�l�b�g�̃X�s�[�h���ƍL�搫�͖����ł��Ȃ��B�p�\�R�������ʓI�Ɋ��p���邱�Ƃ��ł���Η���ɂƂ��Ă����ȗ͂ƂȂ蓾��B�Ƃɂ����A���₻����������Ȃ̂ł���B
![]()
����ƍu�k�̃��[�c�͓������ƌ�����B��������Ō�������Ă��邵�A����ɋ߂��u�k������A�u�k�ɋ߂����ꂪ��������ƁA���E���͔��ɞB���ł���B�����͗���Ƃ̕����傢�ɗD���ł���A���̏�ł͍u�k�t�����|���Ă���B�l�̘b�ɂ��ƁA�u�k�̕��������͑��������炵���A�u�k�t�̐l��������Ƃ��͂邩�ɑ��������������B�Ƃ������Ƃ́A�u�k���痎�ꂪ�h�������ƌ����邩������Ȃ��B
����ƍu�k�̑傫�ȍ��ق́A���ꂪ��ϓI�Șb�|�Ȃ̂ɑ��A�u�k�͋q�ϓI�Șb�|�ł���Ƃ������Ƃ���ł��낤���B����͂��ꂼ��̓o��l���ɂȂ肫���ĉ�b��i�s���邪�A�u�k�͂ǂ��炩�Ƃ����Ƒ�O�҂��T�ς��Ă��銴������B�܂�A����������A����́u���䑕�u�̂Ȃ����ɂ̈�l�ŋ��v�ŁA�u�k�́u�J�������p�̂Ȃ����ɂ̃j���[�X����v�ƌ����邩������Ȃ��B���ہA�u�߃l�^�Ƃ����̂͗��j��̎����⎖���Ɋ�Â����̂��������Ƃ�������̂悤�Ɏv�������B
�u�k�ɓo�ꂷ��l���̃Z���t�͂��Ȃ�ŋ������������̂ɂȂ��Ă���B�n�̌��������q�ɏ悹�Čy���Ɍ��˂Ȃ�Ȃ��B�����������_������A�u�k�̕������������Ƃ������C���[�W�������B�j���Ɋ�Â��Ă���̂ŁA�Տꊴ�͖��킦�邩���m��Ȃ����A���̕��A���͏��Ȃ��B�܂��A�u�k�̓Ɠ��̌����Ƃ��������ĉ��҂ɂ͋K�����������ł���B���̔��ʁA�����������Ƃ������[���͂��邪�A��ϓI�ȉ�b����Ȃ̂ŁA���X���������������Ă����͈�a���Ȃ����������邱�Ƃ��ł���B���������A���������ɂł��o����̂�����Ȃ̂ł���B�u�k�͂����͍s���Ȃ����낤�B
�u�k�̖��͂́A���Y���ƃe���|�ƌ��t�g���̖��ł���B�������A���j�D���ɂ̓X�g�[���[���̂����������v�����낤�B�Ƃ��낪�A����̒��ɓo�ꂷ��u�k�t�i�u�ߎt�j�͂��܂�ǂ������͎Ă��Ȃ��悤���B�u������ݍu�߁v�̌㓡��R�́A�������Ƀg���K���V�̕�����邵�A�u�s���V�v�̕s���V�Ή��͏��ƒ��ɕa�����邵�A���̐g����i�H����j�̌y�c���ւ͊������A�@�وꖇ�œV�䂩��݂����L�l�ł���B���̈����́A�����̍u�k�t�Ɨ���Ƃ̐��͕��z�����̂܂ܔ��f����Ă��邩�̂悤���B
�ŋ߂́A�V�i�C�s�̍u�k�t�������\���Ɍ������n��̍u�k��������肵�āA�܂��܂�����Ƃ̍����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���悤�Ɏv����B�}�X�R�~�̕��y�ŁA���q����̃j�[�Y�����㕨�␢�b���̉�����A�������߂Ă���̂����m��Ȃ��B
�f��u�Q���̔ԁv
�����A����������̍�i���D���ŁA����̗���Ƃ���l���̂��̏������̂ɓǂ�ł��������ɁA�҂��ɑ҂����f��ł���ƌ�����B�܂��A���̌�����}�L�m��F�i�Ð��F�j�ē������ɉf�������Ă��ꂽ�B���I�������͊����̂��܂�A�Ȃ𗧂ĂȂ��������炢�ł���B�f�ς̂q�|�P�T�w��Ȃ̂ŁA���F�C�����Ղ�ȓ��e�ł͂��邪�A�ڂ�w���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȉA���ȏ�ʂ͂Ȃ��A���̃^�u�[����������̂��Ƃ����X�ƌJ��L������M���O�̘A���ɁA���A�u�������o�����B�������̐^���Ƃ�������e�[�}�ɓ����̊ē��A�����܂Ŗ{�����悭���ɂ߂����̂��Ɗ��S����B���ɏ������̃t�@���ɂƂ��Ă͊��҂𗠐�Ȃ��o���f���ƌ����悤�B
�`���̎t���̐������O�̃V�[�������y��h�^�o�^���ɁA�����������܂�Ă��܂��A����悠���Ƃ����Ԃɏ������̖��E�ɂ̂߂荞��ł��܂����B���̉f��͒N�����Ă��U��ڏΕ������ߎt�������f���Ȃ̂͌����܂ł��Ȃ����A�������芪����q�A���Ȃǂ����I���B���̍�i�Ɠ������ɎB�e���ꂽ�푈�A�N�V�����f��u�S���̃C�[�W�X�v�ł̗⍓�Ȗk���N�H����̊�Ƃ͐����̗���ƁE�Ζ����������ƒ���M��̍D���A���̍Ȃ̖ؑ����T�̑̓����艉�Z�A�����āA�S�҂ɂȂ����t���̒���T�V�̂����Ƃڂ������Z�������Ă����B
����u�炭���v��f�i�Ƃ������ʂł́A�ē̉��o�ƒ��傳��̈�̖̂����Z�H�Ƃ��Z��̑��̍������Ƃ���������Ă���Ă���A���V�̉A�C���͔��o���Ȃ������̖���ʂɂȂ��Ă���B����́u�炭���v�������Ƃ��Ȃ��ƌ������́A���̃V�[��������w�y���ނ��߂ɂ��f����ς�O�ɐ���Ƃ����̔����Ă������Ƃ������߂���B
�܂��A�`���V���̎ʐ^�ł��Ȃ��݂̃��X�g�V�[���́u�D�Ԃ������v�����ɑf���炵�����o�������B�u�D�Ԃ������v�Ȃǂ͉��C�Ȃ��q���̂��V�тȂ̂����A�v�������Ȃ��W�J�ɑ唚���A���ꂪ�₪�Ċ����̗܂ɕς���Ă����B�Ƃɂ����A���������Ɋy���߂��i�Ȃ̂����A������Ƃ����������̒m��������A����Ɋy���߂邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�֑��Ȃ���A���̉f��̊��̒i�K�ŁA�X�^�b�t�̕����瓖��ɏ������̏�����ɂ��Ď��₪����A���͂Ȃ��狦�͂����Ă����������o�܂�����B���ꂪ���̍�i�ɂǂꂾ���������ꂽ���͂킩��Ȃ����A�������Ɍg���҂Ƃ��Ă͊�����������A������Ƃ͎����ł�����B
���ƁE�m�Z�ƏE������
������o�[�̐m�Z�ƏE�����a�C�̂��ߐ�������܂����B
���̏E������ɂ��Ď��̃u���O�Ɍf�ڂ����L���ł��B
���@�u���O�u�i�V���̖،ˌ�Ɓv�@�Q�O�O�V�D�U�D�U
����u�ʁv����
�]��𗧂������ɂȂ����i�I�H�@��P�e�B
�ŋ߂͂��낢��Ȏ�ނ̌��藬�s�肾�B���t�[�̃C���^�[�l�b�g����ŗ��ꋦ���Ấw����u�ʁv����x�Ƃ����̂�����B�P������R���܂ł̓�Փx������A���������オ��قǍ����Ȃ��Ă���B����Ɋւ���m�����������̂ŁA�Ȃ��Ȃ������[���B
���N���ɖ{���ł��̌���̃e�L�X�g����������D���̋����{�ʂ�����A�_�����ƂŁA�Ƃ肠�����u�P���v�����Ă݂邱�Ƃɂ����B�C���^�[�l�b�g�Ő������ԓ��ɉ���̂����A���Ȃ�}�j�A�b�N�Ȑ��E�������B���ꋦ���ÂȂ̂ŁA���R�̂��ƂȂ��瓌���̗���┶�Ƃ��ȂɊւ����肪���S���B�������t�@���̎��ɂƂ��Ă͂��Ȃ�s���B�������ԃM���M���ʼn��I���A���ʂ�҂��Ă����Ƃ���A���Ƃ����i�����B

�ł��A���i�؏���������Ă��قƂ�ǃ����b�g�͂Ȃ��B�ꉞ�A���Ԍ���ŗ��ꋦ���Â̊�Ȃ͊������œ����炵���B�ł��A���ł͂܂��g���Ȃ��B�w����u�ʁv����x�ɍ��i��������ƌ����ė��ꂪ��肭�Ȃ��ł��Ȃ����A�{���́u����ʁv�̏ؖ��ɂȂ�킯�ł��Ȃ��B�������A����̐��E�𑽂��̐l�ɂ��L�߂悤�Ƃ�������̎p���͕]���ł��邵�A���ہA����̗��j�ȂǍĔF�����ĕ��ɂȂ����B�l�b�g����̘b��Ƃ��Ď��������b�̃l�^�Ɏg����B
�����̂�����A��x���킵�Ă݂܂��B�@���@����u�ʁv�����@
�y�u���O�u�i�V���̖،ˌ�Ɓv�Q�O�O�W�N�P���P�Q���̌f�ڋL���z
���{���w���m
�]��𗧂������ɂȂ����i�I�H�@��Q�e�B
���{���ɖڊo�߂����A�����Ɠ��{���̉��`���ɂ߂悤�Ǝv���A�Q�N�Ԃ������ĕ����Ď擾�������i���B

�e���@���̕������ƕ�����̉���ɂ���
�y���{���w���m�Ƃ́z
���{��ʐM�u���̑S�ے�������߂ėD�G�Ȑ��тŏC�����A�����I�����I�ȓ��{���̒m���Ƒ̌����C�߁A�������m���Ɓu�V�ѕ��v�E�u���ݕ��v�E�u�y���ݕ��v�L���w���ł��A���{���̐^����������ƔF�߂���l�ɗ^������ď̂ł��B
�ƂȂ��Ă���B
���{���̗��j����A���̑����������旿���܂ŕ�����₷���e�L�X�g�Ŋw�ׂ�B���\���e�̔Z���ʐM�u���������B���i�F����邽�߂ɃX�N�[�����O���Q�����Ȃ���Ȃ炸�A���\�A�l�ł��͂���B
�������A���̎��i�������Ă��A�債�Ė𗧂��Ƃ͂Ȃ��B�ł��A�b�̃l�^�ɂ͏\���g����B
���́u���{���w���m�v�̏�ɂ́u���{���w���t�́v�Ƃ������i������̂����E�E�E
�����̂�����A��x���킵�Ă݂Ă��������B
�@���@���{���w���m�ɂ��ẮA�u�e���@�v�̃T�C�g���������������B
�y�u���O�u�i�V���̖،ˌ�Ɓv�Q�O�O�W�N�Q���Q�P���̌f�ڋL���z
������
�]��𗧂������ɂȂ����i�I�H�@��R�e�B�@
�u�����Z�i�v�I�I
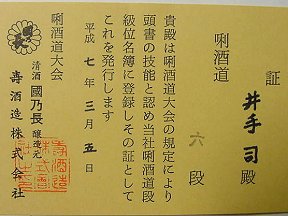
���ւ�Ɂu���v�Ə����āu�����v�ƓǂށB��ʂɂ́u�������v�ƕ\�L���邪�A�����ɂ͌��ւt���B
�ǂ݂��u���������v�ł͂Ȃ��u��������v�Ƃ����炵���B
�u���T���v�ŗL���ȁA���{���Ύs�x�c���̎𑠁u���v��Â̗������̃C�x���g�ŁA�S������Ċl�������B
���͂U��ނ̂������Q�{�������āA���������̑g�ݍ��킹�Ă���̂ł���B
���ꂪ�ȒP�Ȃ悤�ňӊO�Ɠ���B�S��������I�茠���������悤�Ȍ`���ōs����B
������̕��͊m���T��ނłP�O�{�̂����������B�i�������{�������ɉߋ��Q��o�ꂵ�����Ƃ�����j
���́u�����v�Ȃ���̂́A���ƌ���́A������V�тȂ̂����A�b�̃l�^�ɂ͎g����B
���͂��������Ă��A�_����i�A������i�Ȃ̂ŁA���ȏЉ�Ȃł́u�������킹�ď\�i�v�ƌ������Ƃ�����B
�������A�u���̂����̘Z�i�͗����v�ƃI�`�����c�B
����̌��p
���̃u���O�u�i�V���̖،ˌ�Ɓv�ŁA�Q�O�O�W�N�W���Q�O������X���P�P���܂ŘA�ڂ����L���ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�u����̌��p�v�̃y�[�W
�V�N�̂����A�@�i�Q�O�P�O�N�P���P�V���E��T�S�Ύs����ȃv���O�������j
�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�����S�N�i�P�X�X�Q�N�j���犈�����n�߂܂����w���̉�グ�ށx���A���������܂������܂��āA�P�W�N�ڂɂȂ�܂����B�����J�Â̒���́u���Ύs����ȁv�Ɓu�w�O��ȁv���A���킹�ĂP�X�Q��ڂƂȂ�A���ד���҂��{�N���ɂQ���l��˔j���錩���݂ł��B
�@
��������̗���D���̎��ǂ����A���������Ŋy���ނ��߂Ɏn�߂��f�l�̊�ȂȂ̂ł����A���̗ւ��ǂ�ǂ�ƍL�����Ă����āA���ł͑����̂��q����ɂ����ꂢ��������悤�ɂȂ�܂����B�����o�[�ꓯ�A�{���Ɋ��ӂ̔O�ł����ς��ł��B
�u�f�l�̊�ȂȂ̂ɁA�Ȃ��A�����̂��q��������̂��v�Ƃ悭������邱�Ƃ�����܂��B�����̌|�����߂���̂ł���A�������ꗿ���x�����Ăł��v���̊�Ȃɍs�����̂ł��傤���A���̂悤�ɂ킴�킴�A�����̉�ɂ����ꂢ�������Ă���̂́A�f�l�̐ق��|�̒��ɂ��A���ǂ����u�V�ѐS���ꏊ�����Ɋy����ł���p�v�����ۛ����������Ă���̂��Ǝv���Ă���܂��B���ꂩ����A���̊F�l�̂��C�����ɉ�����ׂ��A����w�A�f�l�|�ɖ����������鏊���ł��B
�Ƃ͂������̂́A�F�A�{���̎d���������Ă��܂��̂ŁA�d�����Z�������Ȃǂ́A�d���̍��Ԃ̂킸���Ȏ��ԂɌm�Âɗ��ł���悤�Ȏ���ł��B�ł�����A����������Ȏ��s���J��Ԃ����Ƃɂ��Ȃ�܂��傤���A�F�l�Ƃ��ꏏ�Ɏ�̗�����y����ł��������Ǝv���Ă���܂��B�ȂɂƂ��A���܂łƓ��l�ɂ��ۛ��̒�����낵�����肢�\���グ�܂��B
�v���ƃA�}�`���A�i���̂Q�j
�ǂ�Ȑ��E�ɂ��v���ƃA�}�����݂��܂��B���R�A����̐��E�����l�ŁA���̋��E���͖��m�ł��B
�v���́A������ׂ��t���ɓ��債�A�C�s��ς�Ńv���̉����𖼏�邱�Ƃ��ł��܂��B�����āA����������邱�Ƃł������҂����Ƃ��ł��܂��B����A�A�}�́A���������C�s�ɂ͖����ŁA�D���Ȏ��ɍD���Ȃ悤�ɗ���������邱�Ƃ��ł��܂��B
��������������Ă���̂ł����A���ꂪ�S���Ⴂ�܂��B����̏�艺��͖��ł͂���܂���B�v���Ȃ̂��A�}�Ȃ̂��Ƃ������ƂŁA�����Ǝp��������Ă��܂��B
���l�ɁA���q����ɂƂ��Ă��A�v���̗�����y���ނ̂ƃA�}�̗�����y���ނ̂Ƃ͈�����X�^���X���Ǝv���܂��B�ł�����A�v���ƃA�}�͂��݂��ɂ��̗̈��N���悤�Ȃ��Ƃ͐T�ނׂ����Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
�v���ƃA�}���e���������̂́A���ꈤ�D�ƂƂ��Ă͑傢�Ɍ��\�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B�������A�����ł͑��܂݂���ׂ��ł͂���܂���B�v���ɂƂ��Ă̍����͐E��ł�����A���̓��������ɋC�����A�}����������ׂ��ł͂���܂��A�t�ɁA�v���ɂ����ꂾ���̃v���C�h�������ė~�������̂ł��B
�܂��A�A�}�������̂Ƃ���̓v���ɑ��Čh�ӂ��A������悷�ׂ��ł��B
�y�u���O�u�i�V���̖،ˌ�Ɓv�Q�O�P�O�N�R���Q�W���̌f�ڋL���z
�t���_���X �i�Q�O�P�O�N�W���Q�X���E��T�V�Ύs����ȃv���O�������j
�c�����������\���グ�܂��B
�A�z�Q�[���ł��B�ĂƂ����A�u�����I�v�B�����ƌ����A�u�n���C�v�B�n���C�ƌ����A�����u�t���_���X�v�ł��ˁB�Ƃ������ƂŁA���N���Ă̕������Ƃ�������t���_���X���u���t�A�j�R�E�t���N���u�v����ɂ���I���Ă����������ƂɂȂ�܂����B����łU��ڂɂȂ�܂��B
�@
��ʓI�Ɏ������́u�t���_���X�v�ƌĂ�ł��܂����A�u�t���v���̂��̂��u�x��v�Ƃ����Ӗ��ł��̂ŁA�{���́u�t���v�Ƃ����ĂԂ̂������������ł��B�ł��A���{�ł͐̂���u�t���_���X�v�Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B
�@�u�t���_���X�v�́A�n���C�̗��j�╶���Ɛ[�����т��Ă��܂��B�����������Ȃ������Ñ�̃n���C�̐l�X���A���̐_�b����j���A�Ԃ�C�Ȃǂ̎��R��\������_���X�Ŏq���ɓ`���悤�Ƃ��܂����B���̗x�肪�u�t���v�Ƃ��Đ��E���Ɉ������悤�ɂȂ����̂ł��B
�@
�u�t���_���X�v�́A�ꌩ�D��Ɍ����܂����A�ӊO�Ɖ^���ʂ̑����x�肾�����ŁA�ŋ߂ł̓V�F�C�v�A�b�v��_�C�G�b�g�̂��߂ɂ���Ă�����������悤�ł��B
�@
���āA����́u�t���_���X�v�̋Ȗڂ́A
�@�@�@�P�@�t�@�J�e���e��
�@�@�@�Q�@�u���b�T���i�j�z�C�G
�@�@�@�R�@�w�}�i�I�����I�G
�@�@�@�S�@����̃n���C�q�H
�ȏ�̂S�Ȃł��B
�@
����ƁA�Y�ꂿ��Ȃ�Ȃ��̂��A�u����v�ł��B�����͊�Ȃł�����ˁB�����i������ł͂���܂��A�����������l�^�������肻�낦�Ă���܂��̂ŁA�Ō�܂ł�������肨�y���݂��������B
�v���ƃA�}�`���A�i���̂R�j
�y�����̖��Ƌ����Y�t���̃C���^�r���[����z
�f�l�Ƃ��ĂQ�O�N�R�O�N�Ɨ��������Ă��āA��������̃l�^�������ĂāA��肩�낤�ƁA���F�A�f�l�͑f�l�B
�P�N�O�ɓ��債���O������ɂ͂��Ȃ�Ȃ��B��������Ă����҂ɂ����Ȃ�Ȃ��B
��O�̐l����q���āA����Ŕт�H���Ă����ƕ��𐘂��邩�����Ȃ������B
�f�l�͕��𐘂��Ă��Ȃ��B���Ŕт͐H���Ȃ���B
�ł��A�f�l������ł��闎�������B
�P�@�� �i�Q�O�P�U�N�X���Q�T���E��X�S�Ύs����ȃv���O�������j
�����Ǝ����i�V�����l��ڂ̌j�Ē����P�����邱�ƂɁI �ł��A�P����I�̌���∥�A�͂����ɁA�����Ȃ荂���ɏオ���ė���̃}�N���ŏP���������邱�ƂɂȂ�A��������ׂ낤���傢�ɋْ��B�ӂƋq�Ȃ�����ƁA�S���Ȃ�ꂽ���̌j�Ē��t���̎p���E�E�E�B���ł�˂�I ��Ȃ��قȁI�I �Ǝv�����Ƃ���Ŗڂ��o�߂܂����B�S�āu���v�������̂ł��B
�u���v�Ƃ������̂́A�{���A��z�V�O�Ȃ��̂ł����A����Ȗ�������Ȃ�āA���Ƃ��s���ȋC�����܂��B���̂Ƃ���A�������E���P�����悭�s���Ă���A�ŋ߂ł́A�Ε����O���t���������g�̎t���ł��鎵��ڂ̏Ε����������P������Ƃ����j���[�X������܂����B����Ȃ��Ƃ��L���̕Ћ��Ɏc���Ă��āA����Ȗ��ɂȂ������̂����m��܂���B�s���Ȗ��Ƃ͌����A������Ɗy���������ł����ǁE�E�E�B
�v���̗���Ƃ̐��E�ł́A�喼�Ղ̏P���Ƃ����̂͑傫�ȃC�x���g�ł�����܂��B�����̕��ł́A��������Ƃ��o�����邲�ƂɏP�������邱�Ƃ������A�P���͓�����O�ł����A����ł͂���قǏP���ɌŎ����邱�Ƃ͖��������悤�ȋC�����܂��B�^�ł����x�̖�������ł́A�����܂Ŏ��͎�`�Ȃ̂ŁA�l�C�����̃o�����[�^�[�ɂȂ�܂�����A�喼�Ղɂ͂������Ȃ������̂ł��傤�B�ł��A����ɂ��喼�Ղ͂���܂��̂ŁA�ŋ߂ł́A����ł��u�j�Ě����v�E�u�j���}�v�E�u�щƐ��ہv�E�u�j���V���v�E�u�j���O�v�E�u�������s�v���X�A�p�ɂɏP�����s���Ă��܂��B����́A�u�Ε������߁v�E�u�j�Ē��v�E�u�j�t�����v�A�����āu�j�}���v�Ȃǂ̖��Ղ̏P�����C�ɂȂ�Ƃ���ł��B
���ǂ�������
���ΐN��c������ÂŁA���w����Ώۂɓ��{�̓`���������w�ԃC�x���g���J�Â���A�����Q�������Ă��������܂����B
���@�u���O�u�i�V���̖،ˌ�Ɓv�@�Q�O�P�W�D�X�D�Q�Q
���̉�グ�� �i�Q�O�Q�R�N�V���Q�R���E��P�Q�W�Ύs����ȃv���O�������j
�������́u���̉�グ�ށv�́A���Ύs���������_�Ƃ���f�l����̃T�[�N���ŁA���N�őn�݂���R�P�N�ڂɂȂ�܂��B��̃R���Z�v�g�́A�u������y���ނ��Ɓv�B����ɐs���邩���m��܂���B���q����ɗ�����y����ł��������ȑO�ɁA���Ҏ��g��������y���ނƂ������Ƃł��B
�@
��̒��ŁA�^���t��̂悤�ȏ㉺�W�͍�肽���Ȃ��̂ŁA�㉺�W���������₷���m�É�Ȃǂ͈���܂���B�m�Â͂��ꂼ��̃����o�[�̎��ȐӔC�ł��B�����āA�y������Ȃ��߂������߂ɁA��̃����o�[�̊ԂŔ�排���������A����������������A����I�ȁu�_�������v�Ȃǂ����Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��B
�����̉�̊�Ȃ́A�f�l�|�Ȃ̂ŁA���ꗿ�Ȃǂ��������܂��A�o���҂͖�����d�������ł��B�i�^�c�́A���������j
�@
�l�Ɍ��킹��ƁA�����̉�́A�܂��Ƃɂ��`���T�[�N���Ƃ̂��Ƃł��B�ł��A���`�����炱�����ꂪ�S��y���߂�̂��Ǝv���Ă��܂��B���҂��y���߂Ȃ��ƁA���q�������Ȃ��y���ނ��Ƃ͂ł��܂���B
�@
�܂��A���`����Ȃ̂ŁA����̃��x���I�ɂ͂���قǍ����͂Ȃ��ł��傤�B�ł��A���̑f�l����T�[�N���ƃ��x�����ׂ�K�v������܂��A���\�N�Ƒ吨�̂��q�����t���������Ă��������Ă���̂��A�����̉�̊y�����̉����̏ؖ��ɂȂ��Ă���Ǝv���Ă��܂��B
�@
�Ƃ������ƂŁA�C�̂������A���ƁA���ꂩ������痎����y���݂������̂ł��B
 �@
�@